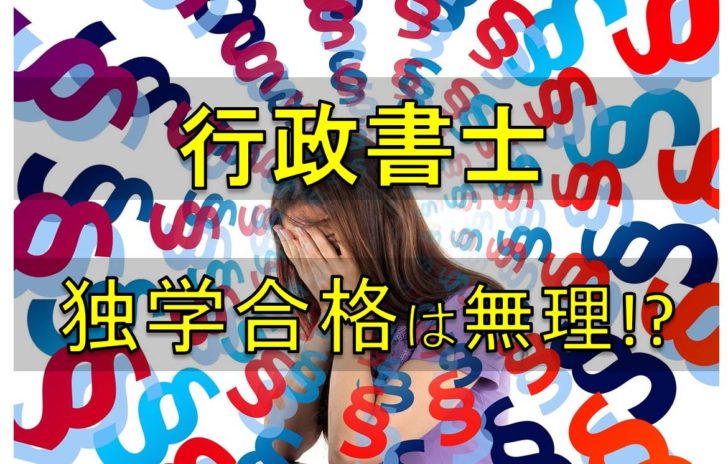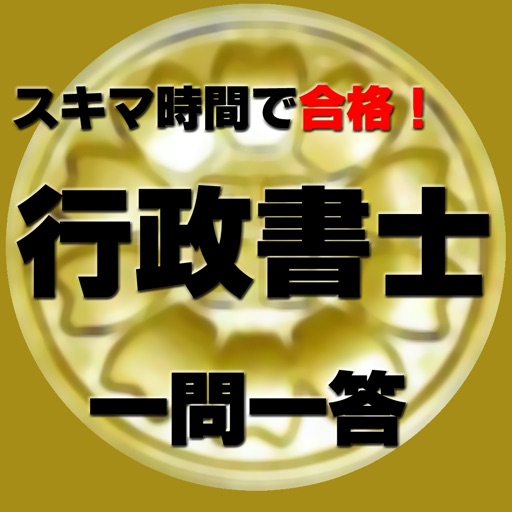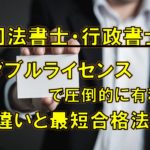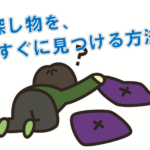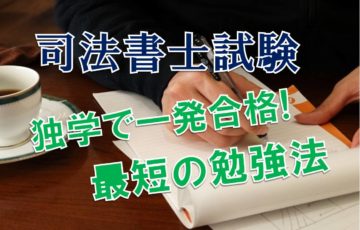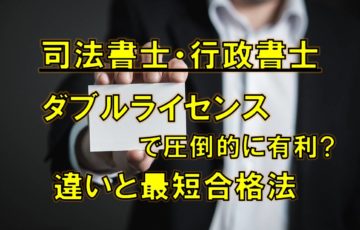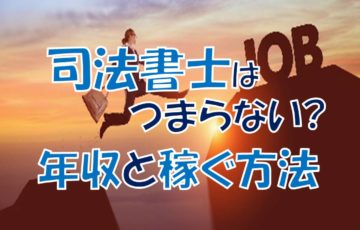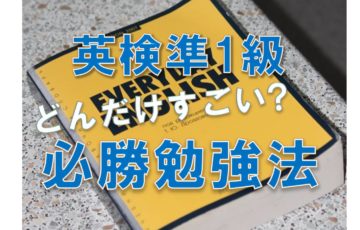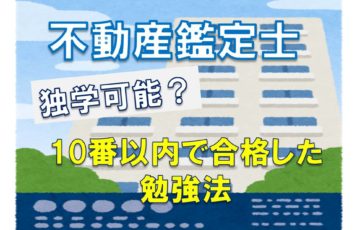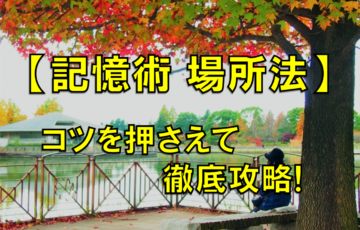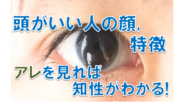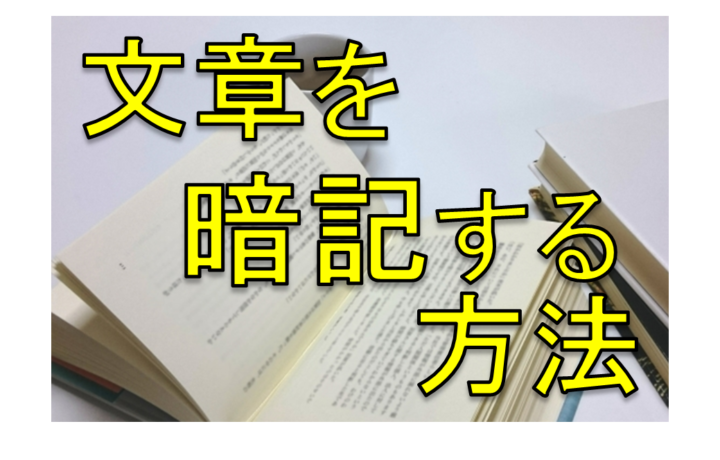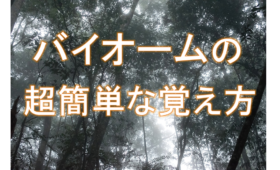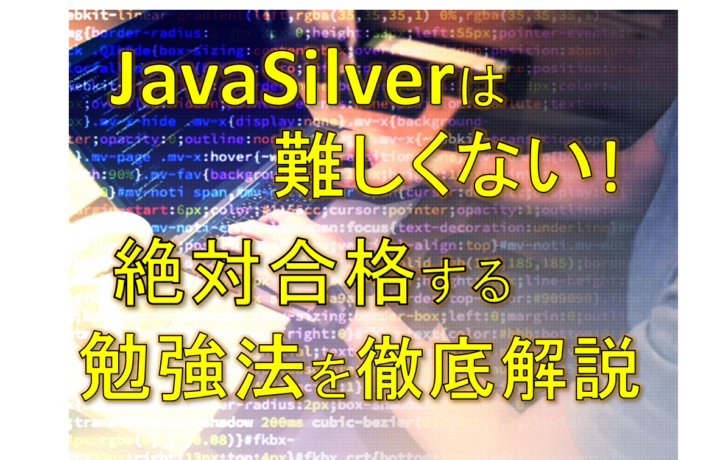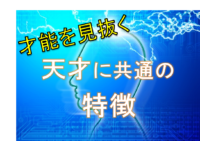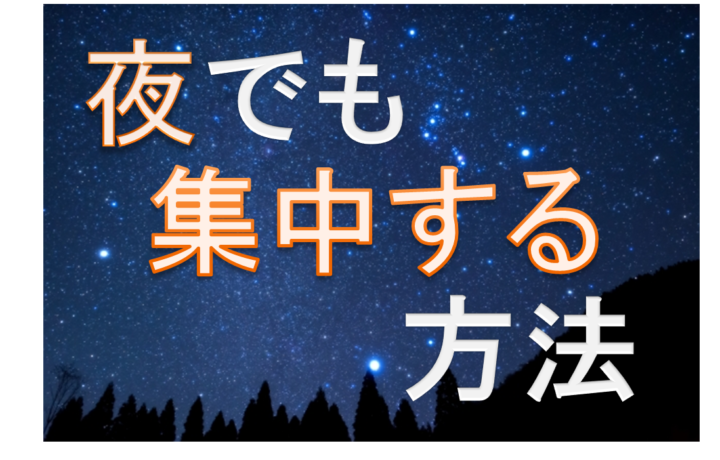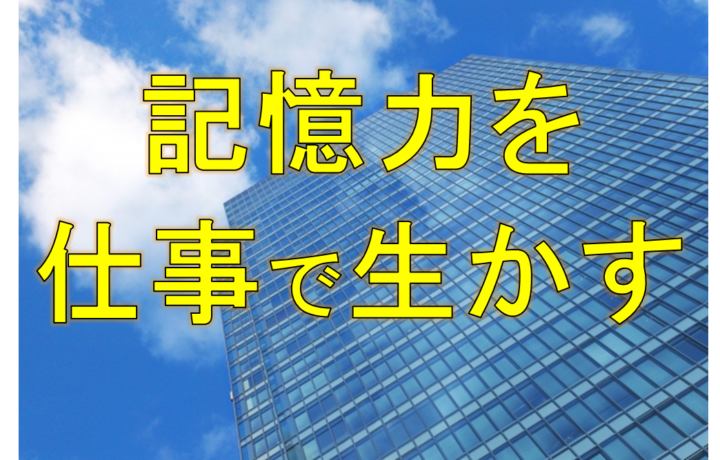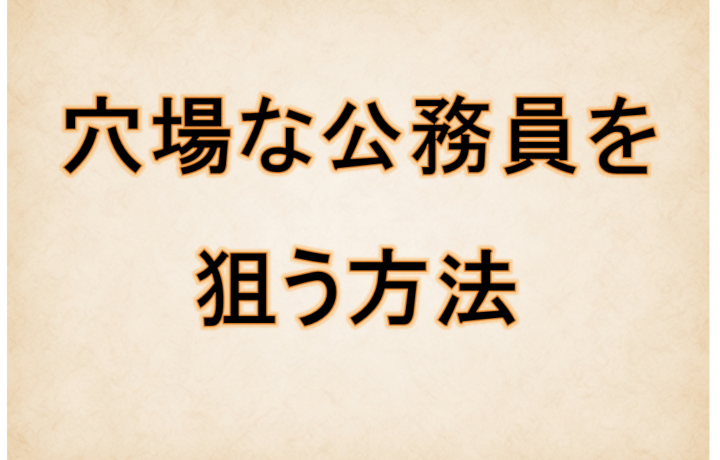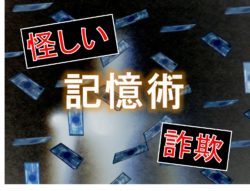こんにちは、笹木です。
今回は行政書士受験にあたって誤解されがちなポイントと、効率的な合格への勉強法について。
法律資格を目指す人の多くが、まず最初に挑戦しようと考えがちなのが行政書士の資格。
「司法書士と比べて合格しやすい」というようなイメージが広まっていることもあり、勉強を始める人も多いけど、実際はそれほど簡単な試験ではない、と個人的に思っています。
むしろ、独学でやってみようと気軽にはじめたものの、やっぱり無理だった、という人は周りに結構いました。
そこで今回は、
特に法律初学者に行政書士試験が独学では本当に無理なのか?行政書士の勉強でよくある誤解と、効率よく合格するにはどうすべきかについて解説していきます。
目次
行政書士の独学合格は無理?10人に1人の合格率
行政書士試験の最近5年の合格率を見ると、だいたい8%~15%の間で推移。
行政書士試験試験は法律科目と一般常識科目でそれぞれ決められた基準点を取った上で300点満点中180点以上の得点で合格です。
試験の難易度にかかわらず、この決められた得点を上回らいといけないんです。
つまり、簡単な年に当たればラッキーだけど、難しい年に当たると途端に合格率が下がる。安定的に得点できるような実力がないと、短期で合格することは難しいです。
逆に、簡単な年だと合格しやすかったりする。これは資格試験にはよくあることだけど、一番危険なのは、「行政書士なら独学でもいけるかも?」という生半可な気持ちかなと思います。(そういう人ばっかり、途中であきらめていく人が体感として多かった)
まず独学で合格を目指すなら、受験者の多くが不合格になる試験だ、楽に受かろうとするのは無理だ、という意識が心構えとして重要です。
独学では忍耐力は必須!行政書士の多様な法律科目
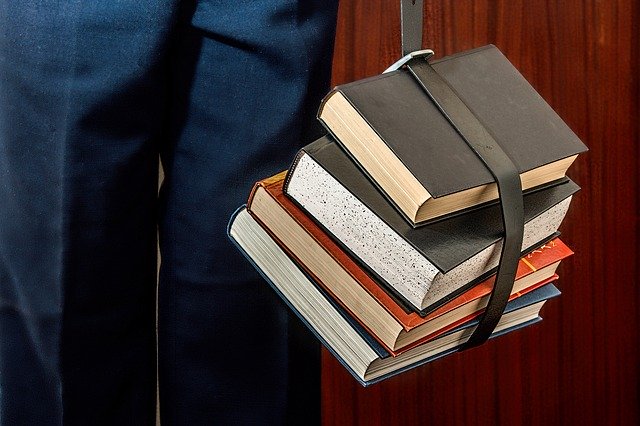
行政書士試験の対象となる法律は憲法・民法・行政法・商法・会社法。
どれも司法試験の科目にも入っているメジャーな法律です。だけど、法律初学者にとっては、どの法律も攻略するのはまあ大変な科目になると思います。
憲法は膨大な判例理論があるし、民法や会社法は約1000条にもなる範囲の広い法律。何より一番大変なのが行政法。
行政書士試験の法律科目の全46問中22問が行政法から出題されるんです。つまり、問題の約半分が行政法からの出題ってこと。
え?逆に行政法だけ極めれば楽なんじゃない?
と思うかも。ところがそうじゃないんです。
そもそも行政法といってるけど、「行政法」という名の法律は存在しない。行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法などの行政に関する法律をひっくるめて「行政法」といってるんです。
ということは、行政法分野だけでも多岐にわたる法律を攻略しなければならない。これが出題の主力となると、1つの法律たりともおろそかにすることはできないんですよね。。
こういった勉強しなければいけない法律の多さが、最初こそ「行政書士なら独学でいけるかも?」と思っていた受験者が、無理難題な試験じゃないかと諦める要因になっているんだろうなと思います。
独学で全範囲は無理?行政書士の一般知識科目
一般知識と呼ばれる一般常識科目も勉強するのほ意外と厄介。
出題範囲は、「政治・経済・社会」、「情報通信・個人情報保護」、「文章理解」の3分野なんだけど、とっつきにくく、どう手を付けていいかに苦戦する人も多いです。
というのも、政治学、経済学に関しては範囲がかなり広く、これを独学で全部潰していくなんて無理じゃない?と思う人がほとんどだと思う。
また、情報通信・個人情報保護といわれても、前提知識がない人にとっては、具体的に何を勉強すべきかがわからないと思うし、時間も取られます。
文章理解だけが唯一、国語の問題なのでそれほど勉強する必要がない分野。ここは独学でも無理なく進められます。
と、まあ大半が独学だと勉強しにくい一般常識科目だけど、捨てるわけにもいかないんですよね。一般常識科目でも一定の点数を取らなければ合格できないのが行政書士試験。独学でも対策は必須です。
初心者では無理!行政書士試験の40字記述式問題
また、行政書士試験を難しくしてるのが、択一式の問題ばかりが出題されるわけじゃないこと。
一定の設問に対する解答を40字前後で記述しなければならない形式が、行政法から1問、民法から2問必ず出題されます。
しかも、1問20点と、択一5問分くらいの高い配点になってるので、絶対捨てるわけにはいかない。記述式って本質的に法律が分かっていないとなかなか書けないので、ノリで回答としようとしてもほぼ無理。
40字前後なら、いけるんじゃない?と思うかもしれないけど、字数を制限されるのって逆に難しいんです。法律に詳しい人でも結構苦戦する人が多いです。
だって、択一式だったら独学でも全然行けると思う。だってカンで当たる可能性があるんだから。でも記述式の場合、当たり前だけど、よくわかんないけどたまたま正解するって無理ですよね。
この40字の記述問題も、行政書士試験を難しくしている部分だと思います。
行政書士を独学で無理なく進める勉強法

ここまで独学では難しいポイントをあげてきましたが、実際に行政書士を独学で合格するのは無理なのか?
というと、そんなことはないです。「そんなに難しくないんじゃないか?」という前提で独学を始めようとすれば、無理なのかもしれないけど、着実にコツコツと積み上げられる人であれば無理なんてことは全然ないと思います。
そんな独学での合格を強力にアシストする、おすすめの勉強法を紹介します。
無料アプリで独学
独学で大事なのは、モチベーションと効率的な勉強法。アプリを活用するだけで、かなり効率的に学習を進められます。無料アプリだとこちらがおすすめ。その名の通りスキマ時間を活用して過去問を解けちゃうのでかなりおすすめ。しかも試験日までの日数と自分がどのくらい進んだかも確認できるので、独学で合格を目指すにはもってこいの行政書士の過去問アプリです。
youtubeを活用して独学で動画学習
youtubeを活用するというのも手。最近では本当に動画が充実していて、独学をしていきたい人にとってはとても勉強しやすい環境だと思います。動画だと、直感的な好き・嫌いもモチベーションに関わるので自分にあった人を見つけてみてください。
ただ、怖いのがyoutubeでそのまま無関係な動画をダラダラと見てしまう可能性が高いってこと。紹介しておいてなんですが、これは本当に気をつけた方がいい。youtubeに時間を取られてしまいがちな人は活用しないほうがいいです。
記憶術の活用
独学では勿論、どんな勉強の仕方をするにせよ、習得しておいた方がよいと個人的に思うのが、記憶術。行政書士の勉強との相性もすごく良く、勉強時間を大きく削減することができます。一度知ってしまえば一生使えるスキルで、他の資格試験や他分野にも応用できるのがよいところ。実際、僕は色んな資格試験に応用し、今までとは比較にならないほど短時間の勉強で効率よく合格できるようになりました。
ちなみに、僕が利用していた記憶術はこちら。よければ参考にしてみてください!
行政書士の独学合格は無理?まとめ
ここまで行政書士の独学が無理だと挫折してしまいがちなポイントをざっくりまとめると、
・予想より合格率が低く、楽に受かるのは無理
・種類が多すぎて挫折しやすい行政書士の法律科目
・独学で網羅するのが難しい一般常識
・独学では攻略が難しい40字記述式問題
この4つが行政書士試験を、難しい、独学では無理だと思わせる要素です。
そして、独学で一発合格を目指すならば、無料アプリや、youtube、記憶術の活用もおすすめ。
記憶術を使えるだけで、独学の勉強を大きく効率化してくれます。司法書士や行政書士との相性もいいので、習得できると、今までの勉強はなんだったんだというくらい効率が変わりますすよ。
行政書士合格への勉強で一番大事なのは、簡単に合格できそうと、甘く考えないことだと思います。おそらく、予想以上に面倒くさい部分もあると思うので、予め「地道な勉強が必要」という覚悟を持って勉強を進めれば、結果的に一発合格もできます。
頑張りましょう!
おすすめ記事
勉強嫌いで、何をやっても上手くいかない、
コンプレックスの塊だった僕が、
どうやって記憶術で人生を変えられたのか。その理由を以下の記事で公開しています。